連載「電子楽譜のはなし」
この記事をご覧になっている方なら、どこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。“電子レンジ”でも“電子ピアノ”でもない“デンシガクフ”。言葉の響きからして何だかむずかしそう・・・。
「楽譜はやっぱり紙、電子楽譜なんて縁のないもの」とお思いのあなたも、きちんと知れば、“電子楽譜”との理想的な付き合いかたにきっと気づくはず。
Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?

前回は、“電子楽譜って何?”と題して、楽譜の歴史を振り返りつつ、いよいよ一般的に普及が進む電子楽譜とは一体どんなものなのかを概観してみました。
今回は、楽譜を電子データで扱えるようになるとどんな便利なことがあるのか、メリットを具体的に見ていくと同時に、紙の方が優っている点も挙げ、私たちはこれから紙の楽譜と電子楽譜のどちらを選んでいくべきなのかを考察してみましょう。
ー目次ー
1. 電子楽譜のメリット
2. 電子楽譜のデメリット
3. 紙の楽譜のメリット
4. 紙の楽譜はどこへ行く?
5. 関連記事リンク集
1. 電子楽譜のメリット
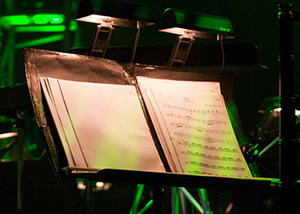
まず、電子楽譜のメリットを列挙します:
- 編集が容易 もはや言うまでもなく、コピー&ペーストなど編集が容易なことは、電子楽譜ならではの大きなメリットです。詳細は別編《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》シリーズをご参照ください。
- 音が出る 現在の電子楽譜は、多くがPDFデータですので音を聴いてみることはできませんが、楽譜ビューワーを使えば、楽譜を閲覧するだけでなく、再生して音を聴くことができます。
- 二次的利用が可能 過去に演奏した楽譜を移調したり、別アレンジを施したりと、後から手を加えることが可能です。
- 新しい表現の発生 音だけでなくアートワークやリンク情報を盛り込んだ楽譜など、紙の楽譜ではあり得なかったようなマルチプルな表現の可能性が広がります。
- 暗がりでの視認性 照明が落とされた暗い所で演奏するケースがあります。例えばオーケストラ・ピットでのオペラ演奏や、夜の屋外でのジャズ演奏など。従来だとそんな場合には手元を照らす照明灯を使ったりしますが、タブレット型端末ならばその必要はありません。
- 譜めくりの新しい形 特に演奏時に両手が塞がっている楽器にとって、譜めくりは演奏内容にまで影響してしまうほど重大な問題です。フットペダルで踏めくりをしたり、手をかざしたり首を傾けることで譜めくりを行えるなど、新しい譜めくりのスタイルが生まれています。
- 拡大縮小、視覚弱者対応 画面に表示された楽譜を拡大縮小させるのはお手のもの。まだ実際には見たことはないですが、視覚弱者の方向けに黒背景に白い楽譜を表示させるようなことも実現可能でしょう。
- 柔軟に印刷 印刷すれば、従来型の紙の楽譜として利用可能。必要な部数を必要なサイズで印刷することが可能。
- 劣化しない/バックアップが容易 紙と違って、データは経年劣化や複製による劣化がありません。外付けHDDやクラウドなどに適切にバックアップを作成することで、紛失などのリスクを防ぎやすくなります。
- 検索性 楽譜に限らず、データの利点として検索性に優れることが挙げられます。曲名や作曲家名で手持ちのライブラリーを検索したり、将来的にはメロディー検索などもできるようになっていくのでしょう。
- 省スペース/持ち運びが簡単 楽譜がすべてデータ化されたら、分厚い楽譜ファイルも楽譜棚は必要ありません。記録媒体の容量が許す限り、数千曲でも数万曲でもモバイル・デバイスにコピーして持ち運べます。
- 人との受け渡し(共有)が簡単 楽譜データをメールでやりとりしたり、クラウドサーバーに置いて共有したり。
- コンテンツの入手方法に革新 楽譜屋さんに足を運んだり、最近ではオンラインショプで購入するのが当たり前だった楽譜ですが、ダウンロード販売などの新しいサービスの出現により、欲しいと思ったらすぐに目的の楽譜を手に入れることができるようになりました。
- 新しいビジネス形態の発生 従来型の楽譜出版でコストの大部分を占めていた「印刷」を省くことで、楽譜配信サービス、オンデマンド出版、電子自費出版など、今まで実現できなかったような出版活動が可能に。
(1)作曲&アレンジで
(2)演奏現場で
(3)データの整理で
(4)他者との共有で
2. 電子楽譜のデメリット

それでは、逆にデメリットを考えてみましょう。挙げてみると少なくはありませんが、ここに挙げたことはテクノロジーの進化により解決できることもありそうです。
- 端末による制限 パソコンの画面やタブレット型端末等に表示させて楽譜を使用する場合には、ハード的な制約、つまり画面サイズや重さ、操作性の問題などで用途が制限されてしまうこともあるでしょう。
- 広げられない 複数ページを机の上に広げて全体を確認したり、複数の楽譜を並べて選曲を検討したり…。よくあるシーンですが、1〜2ページ程しか表示できないタブレット型端末では、このような使い方は難しいでしょう。
- 楽譜内の任意の箇所に移動しにくい 例えば、スコアの6ページ目と35ページ目にあるフレーズを比較したい場合など、今ある電子楽譜ビューワーでは操作がかえって煩わしくなります。
- 脳内で全体像をイメージしにくい 「3ページ目の一番下の段にあったあのフレーズ」というように、人間はとある一部分を「全体の中のこの辺り」というように、脳内で映像として把握したります。どの曲も単一ページで似たように表示される電子楽譜では、このように全体像をイメージすることが難しいかも知れません。
- 目の疲労 電子楽譜をパソコンやタブレット型端末のディスプレイで見る場合、紙で見るより目には優しくないでしょう。バックライトを使えば暗い場所での演奏には便利ですが、長時間の演奏は厳しそうです。
- 不具合の不安 本番中にデバイスが突然機能しなくなったら…、バッテリーが切れてしまったら…、そういった不具合に対する不安がつきまといます。
- 取り扱いを慎重に 紙の楽譜であれば、バッグに無造作にしまったり楽器ケースのポケットに入れたりと取扱いが簡単です。でも電子楽譜を表示する端末は精密機械ですから乱暴に扱うわけにはいきませんね。
- データ消失の不安 操作ミスや不具合でデータが消失してしまう可能性は常にあります。分散管理などでバックアップを適切に行っていないと、数万曲の楽譜が一瞬で跡形も無く消えてしまうことだってあるわけです。
- 提供元消失の不安 例えば、ハードウェア、ソフトウェア、楽譜データ販売などの提供元がサービスを終了してしまったらどうでしょう。もし手元にバックアップできない場合、数万曲のライブラリーも道連れになってしまいます。
- 著作権の問題 紙の楽譜も違法コピーによる著作権問題が常に隣り合わせですが、楽譜をデータで扱うようになると、コピーが容易であること、コピーで劣化しないことなどの特性が逆に災いし、紙以上に著作権侵害のリスクが高まります。一口に著作権と言っても、例えば公衆送信権や送信可能化権などデジタル時代に合わせて規定された新しい著作権法もあります。今まで以上に利用者のモラルが問われます。
(1)作曲&アレンジで
(2)演奏現場で
(3)データの整理で
(4)他者との共有で
3. 紙の楽譜のメリット

では最後に、どんなにテクノロジーが進化しても電子楽譜に紙の代理は果たせないこと、「紙じゃなければダメなんだ!」といった点を挙げてみましょう。
- 紙にしか無い風合い 楽譜の出版社は、自社出版物で使用する楽譜記号のフォルムや文字類のフォント、印刷する紙質に至るまでそれぞれにこだわりを持っており、それが各出版社のカラーや独特の風合いを醸し出しています。表示形態が画一化された電子楽譜には到底真似できないことでしょう。
- 所有する喜び あこがれのアーティストの楽譜集、海外から苦労して取り寄せた大好きなオペラのスコアなど、物質的に所有すること自体が喜びでもある楽譜があります。これも同様のことを電子楽譜に求めるのは難しいでしょう。
- 刻まれる思い出 例えばコンクールに向けて一生懸命練習したあの曲。楽譜には隙間が無いくらい書き込みがびっしり。先生からOKをもらった日付が書かれていたり、仲間からもらった励ましのメッセージが残されていたりと、楽譜そのものが思い出のアルバムになっていることもあるでしょう。いくら電子楽譜ビューアーに書き込み機能が充実しても、紙には敵いません。
- 手稿譜の文化的価値 作曲活動が、Finaleを含む楽譜作成ソフトウェアですべて行われるようになると「手稿譜」が無くなってしまうことになります。これはちょっと寂しい気もします。
4. 紙の楽譜はどこへ行く?

電子楽譜が発達すると、紙の楽譜が無くなってしまうのではないか?と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、こうしてメリットやデメリットを並べてみると、どんなに電子楽譜の世界が進歩していっても、紙の楽譜が無くなることはないと断言してもいいでしょう。
むしろ“紙の良さ”や“紙ならではの利点”がよりクローズアップされ、今後もずっと共存していくはずです。紙の質感、匂い、風合いは、電子楽譜には絶対に出せません。
資料的に手元に大量に持っておきたい楽譜などはデータで充分用をなすでしょう。一方、これから長く取り組もうとしている練習曲は紙に印刷して、お気に入りの厚紙に貼って製本して従来通りの方法で使う方が良さそうです。
結局のところ、TPOに合わせて一番適した形のものを自分なりに選択して、複合的に利用するのがこれから主流になっていく楽譜スタイルということになるのでしょう。紙の楽譜と電子楽譜を併用することで、より効率的に音楽を楽しんでいきましょう!
次回は、具体的な活用事例「Vol.3 電子楽譜最新事情2013」
お楽しみに!
5. 関連記事リンク集
《連載「電子楽譜のはなし」》
- Vol.1:最近よく耳にする“電子楽譜”ってなに?
- Vol.2:“電子楽譜”のメリットとは? 紙の楽譜は無くなっちゃうの?
- Vol.3:電子楽譜最新事情
- Vol.4:Finaleを制するものは電子楽譜を制す!?(最終回)
《連載「楽譜浄書のはなし」》
《連載「DTMのはなし」》
《楽譜作成ソフトウェアの導入メリットを考える》
- 濱瀬 元彦氏:ベーシスト/音楽理論家/音楽教育家 Finaleでビ・バップのフレーズをデータベース化し研究に利用、成果を取りまとめ「チャーリー・パーカーの技法」を上梓
- Shota Nakama氏:作編曲家/オーケストレーター/プロデューサー/ギタリスト 楽譜作成ソフトウェアの編集機能を活かし、オーケストラ・レコーディング用の大量の楽譜を読み易く、超高速で制作
- ジョナサン・ファイスト氏:バークリー音楽大学教官 1学期12回にわたりFinaleを用いた記譜法を学べるオンライン・コースを開講している米国ボストンの名門、バークリー音楽大学(Berklee College of Music)での事例から、楽譜作成ソフトウェアを音楽教育に導入するメリットを考える
《Finaleの基本操作を学べるリソース》
- 譜例で操作方法を検索:Finaleオンライン・ユーザーマニュアルより。Finaleで可能なこと、それを行うための操作法が一目で分かり、初心者の方には特にお勧めです。
- クイック・レッスン・ムービー:Finaleの操作方法や便利な機能などを30〜60秒程度の短い映像でご紹介しています。


